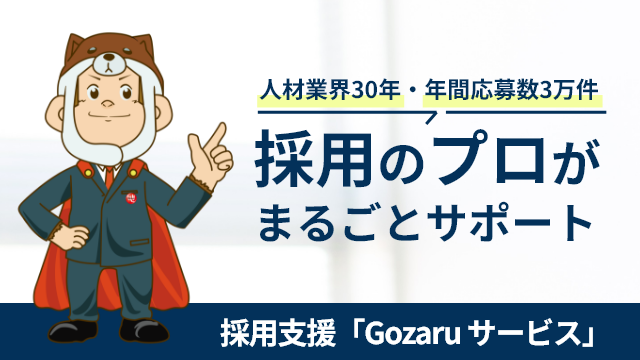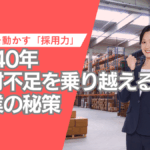2025年4月1日から、職業安定法の改正により「募集情報等提供事業者」および「職業紹介事業者」が、労働者になろうとする者(以下、求職者)に対し、金銭やギフト券、商品券等の提供を行うことが原則禁止となります。これにより、いわゆる「入社祝い金」「就職祝いキャンペーン」などの名目で金銭的なメリットを提供していた手法が、法律で規制対象となりました。
本改正の対象には、求人メディアや人材紹介サービスを提供する企業が含まれます。中には、企業側が「採用広告の一環」として入社祝い金を支出することにより、費用対効果を追求していたケースもありました。しかし、入社祝い金が本来の職業選択の自由を阻害する恐れや、短期離職を助長するリスクが懸念されてきたのです。
本記事では、今回の法改正の背景や具体的な規制内容、そして中小企業の採用活動における影響や対応策について、採用担当者視点から分かりやすく解説します。
なぜ「入社祝い金」が禁止されたのか
「入社祝い金」の提供は一見、求職者にとってメリットが大きいように見えます。しかし、その裏にはさまざまな問題点が潜んでいました。
職業安定法改正の根本的な目的は、労働者が適性や希望に基づいて職を選ぶ自由を保障し、不当な誘導を防ぐことです。
以下の3点が、法改正の背景として重視されています。
- 短期離職の増加リスク
金銭目的で入社するケースでは、職場への適応意欲や継続的な就業意識が薄れがちです。特に、紹介料を目的とした事業者による過剰な入社祝い金の提供は、短期離職を招き、企業にも求職者にも悪影響を及ぼします。 - 本来の職業選択を妨げる可能性
求職者がスキルや志向ではなく、金銭的な報酬に目を奪われると、本来の適職選びが困難になります。結果として、ミスマッチや職場不満、再離職の連鎖が発生します。 - 健全な採用市場の崩壊
人材紹介業者同士が「祝い金競争」をすることで、紹介手数料の高騰や採用単価の肥大化が起き、採用活動全体が金銭誘導に偏重してしまいます。これを是正する必要があると判断されました。
禁止対象となる「募集情報等提供事業者」とは?
ここでのポイントは、「禁止される対象」と「金銭を受け取る対象」です。
- 禁止対象となる事業者
職業紹介事業者(有料・無料を問わず)
募集情報等提供事業者(求人広告媒体やWeb求人プラットフォームなど)
いずれも、厚生労働省の認可または届出制のもとで事業を行っている企業であり、求職者に情報を届ける立場にあります。これらの事業者が、直接または間接的に、金銭やギフト券等を提供することが禁止されます。
- 禁止される対象と範囲
・求職者本人
・内定者
・就職・転職が内定しようとしている段階の個人
特に注意すべきなのは、金銭でなくても「相当価値のあるモノ」(例えば電子マネー、ポイント、ギフトコードなど)も禁止されるという点です。
「入社祝い金」依存の採用から起きていた問題
実際に「入社祝い金」を用いた採用には、企業にとってのリスクも数多く存在していました。
- 本音は“定着”ではなく“即採用”?
中途採用市場では即戦力を求めるあまり、企業側も「とにかく入社してもらう」ことを重視しがちでした。その結果、待遇や制度よりも「手っ取り早い金銭インセンティブ」に頼る構造が進行し、求職者との関係も短期化していました。
- 採用コストが膨張
祝い金制度は多くの場合、企業から紹介会社に支払われる成功報酬から原資をねん出しています。これにより紹介会社は祝い金を宣伝し、より多くの候補者を集めようとします。しかし、その分だけ採用単価が高くなり、コストパフォーマンスは悪化します。
- 社内の公平感の崩壊
既存社員との給与・処遇の不公平感を生むのも問題です。「入社時だけ特典がある」という制度は、社内のモチベーション低下や不信感につながります。
法改正後に企業がとるべき採用戦略
法改正を受け、企業側も採用方針の見直しが求められます。特に中小企業では、リソースに限りがある中で「採用の質」をどう担保するかがポイントです。
- 求職者の“志望動機”を引き出す設計へ
企業理念や成長ビジョンの提示
社内のリアルな雰囲気が伝わる採用サイトの整備
現場社員との面談機会の創出 - 定着を見越した「オンボーディング強化」
採用から入社後数ヶ月までの「育成・支援」フェーズを充実させることが、離職防止には効果的です。制度・文化・業務の3点を軸に設計し、求職者に「自分の未来が描ける」ような環境づくりが大切です。 - 評価される福利厚生・働き方改革
フレックスタイム制やリモート勤務の柔軟対応
時短勤務制度や産育休の整備
資格支援・スキルアップ補助制度の導入
金銭的な誘導が使えない今だからこそ、「本質的な働きやすさ」を提示することが、求職者に響きます。
テキストで理解する三者関係
今回の法改正の正確な理解には、「募集主」「募集情報等提供事業者」「求職者」の関係を明確に把握することが必要です。
- 募集主(企業)
採用を希望し、求人を出稿する立場。広告費や紹介料を支払う。
- 募集情報等提供事業者(媒体・紹介会社)
企業から費用を受け取り、求人情報をWebサイトや広告で発信。紹介が成立すれば、成功報酬を受け取る。
- 求職者(労働者になろうとする者)
媒体や紹介会社を通じて求人情報を受け取り、応募・選考を経て入社。
この三者の間で、「中立的かつ公正な情報提供」が守られることが、職業安定法での基本原則です。金銭提供が加わると、その中立性が揺らぐため、法律で明確に禁止されるに至りました。
注意すべきポイントとグレーゾーン
金銭以外のプロモーション手段にも注意が必要です。
○:企業から直接、社員紹介制度として既存社員にインセンティブを支給すること(内部的)
×:紹介会社が「紹介された求職者」本人に金銭を還元する行為
特に問題になりやすいのは、「ポイント付与」「Amazonギフト券配布」「QUOカード進呈」などが、法の定義上では「金銭等」に該当するという点です。
まとめ
「入社祝い金」という手法に依存していた時代は終わり、これからは企業の真の魅力が問われるフェーズへと移行しています。
中小企業にとっては、派手なキャンペーンを打ち出すよりも、「なぜこの会社で働くべきか」という本質的なメッセージが求められます。
採用は、企業にとって単なる労働力の補充ではなく、「仲間を迎える営み」です。短期的な数合わせではなく、長期的な信頼関係を築ける人材との出会いを目指しましょう。
出典:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html
https://saiyo-kakaricho.com/wp/signing-bonus2025/
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/oiwaikin-2025/