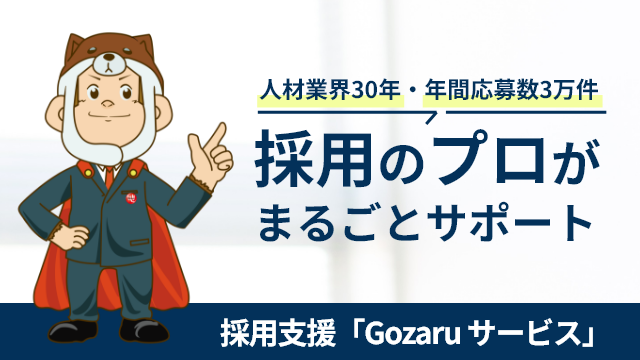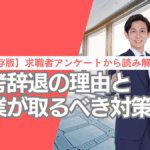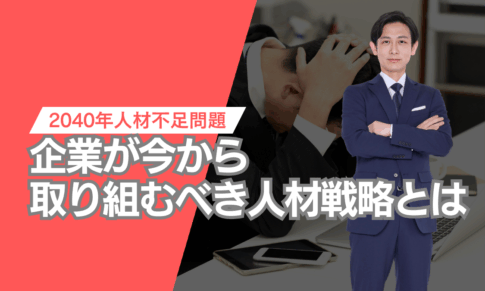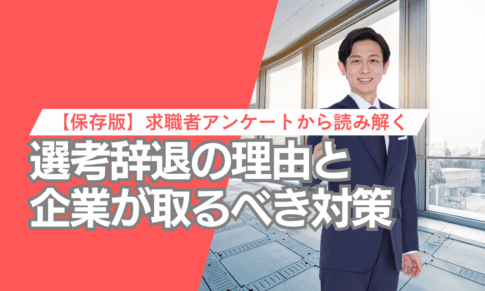「良い人材を採用したいけれど、なかなか応募が来ない」——そんな声をよく耳にします。
特に中途採用においては、求人を出した時期と求職者が動くタイミングが噛み合わないことで、せっかくの採用機会を逃してしまうケースが少なくありません。
2025年現在、中途採用市場では企業・求職者ともに選択肢が増え、採用活動の設計がますます重要になっています。
中小企業では、大手企業のように常時募集を行う体制を整えるのが難しいため、「求職者の動き方に合わせた計画的な求人設計」が結果を左右します。
この記事では、求職者が実際にいつ転職活動を始め、どのような入社時期を想定しているのかを月別に整理し、企業側がいつ・どのように動けば採用につながりやすいかを解説します。
中途採用における求職者のスケジュール例
- 1月から転職活動を開始する求職者のスケジュール
1月から転職活動を始める求職者は、冬季ボーナスを受け取った後に退職を検討し、4月入社を希望するケースが多いです。4月入社を実現するためには、3月初旬までに退職の意思表示が必要となるため、1月・2月の2ヵ月間が活動の中心となります。この時期に転職活動を開始する求職者は意欲的であり、他社より早く求人を見つけてもらうために、企業側も年明け早々から求人公開の準備を整えておくことが求められます。
★対応ポイント:「スタートダッシュ」がカギ
このタイミングの求職者は転職意欲が高く、すでに複数の求人に目を通しています。1月上旬から求人を出しておくことで、「最初に見つけてもらえる」可能性が高まります。
選考スピードの速さと、応募から内定までのリードタイム短縮が重要です。
- 2月から転職活動を開始する求職者のスケジュール
2月から転職活動を始める求職者も、4月入社を希望するケースが多いです。しかし、4月入社を実現するためには、3月初旬までに退職の意思表示が必要となるため、活動期間は実質2月の1ヵ月弱となります。この短期間での転職活動では、企業側の迅速な対応が求められます。選考フローの短縮や結果連絡のスピードアップにより、求職者に選ばれやすい企業となることができます。
★対応ポイント:「迅速な対応」がカギ
この時期の求職者は、スピード感をもって選考を進めてくれる企業を好みます。一次面接から内定通知までを最短ルートで設計するなど、選考の短縮がポイントになります。
- 3月から転職活動を開始する求職者のスケジュール
3月から転職活動を始める求職者は、すぐの転職ではなく、良い転職先が見つかり次第、入社を希望するケースが多いです。特に入社時期を決めず、じっくり自分が納得する企業に出会えるまで転職活動を継続する傾向があります。このような求職者に対しては、自社の魅力や熱量を存分に伝えることが重要です。企業のビジョンや働き方、成長機会などを明確に伝えることで、求職者の関心を引き付けることができます。
★対応ポイント:「魅力発信力」がカギ
じっくり型の求職者には、「自社の魅力をどれだけ丁寧に伝えられるか」が決め手になります。仕事内容だけでなく、会社の雰囲気や働く人のリアルな声なども交えて情報発信を行いましょう。
年間を通じた採用計画の重要性
通年採用が一般化する今、求職者の動きは「特定の時期」だけに集中するとは限りません。
とはいえ、実際には1月~3月、6月、9月など、ボーナス支給月や異動・転勤のタイミングを意識して活動する人が多く、求人市場には周期的な波があります。
採用競合と差をつけるためには、この波を読み、求職者が動き出す前に情報を届ける工夫が求められます。
たとえば以下のような取り組みが効果的です。
・自社ホームページでの先行告知(予告型求人)
・スカウトメールやDMを活用した情報発信
・現職中の求職者に向けた「入社時期相談OK」「選考日程柔軟対応」などの文言
また、採用フロー自体も柔軟に設計することが重要です。1~2週間以内で内定が出せる体制や、一次面接をオンライン化するなど、応募から内定までのスピード感を高めることで、求職者の関心を維持しやすくなります。
転職市場の変化と今後の見通し
リクルートワークス研究所の「中途採用実態調査2023」によれば、2022年後半から中途採用を再開・強化する企業が増え、転職市場が再び活性化しています。コロナ禍の影響で採用を控えていた企業も、2023年以降は人手不足や事業拡大を背景に中途採用ニーズが高まっています。
中でもIT・建設・医療・物流といった業界では、慢性的な人材不足により、通年で積極的に採用活動を行う傾向が顕著です。一方で、製造業や販売業などでは、年度末や繁忙期の直前に求人が集中する傾向も見られます。
2025年においても、以下のようなキーワードを意識した採用計画が求められるでしょう。
・ジョブ型採用の浸透
・副業・兼業人材の活用
・オンライン選考の標準化
これらの流れを踏まえて、採用スケジュールを画一的なものではなく、業界特性や自社の実情に応じた柔軟な戦略設計を行うことが不可欠です。
求人企業数の推移と業界別動向
2023年から2025年にかけての業界別求人数の推移をみると、それぞれの業界で異なる動きが見られました。
- IT業界
2023年初頭から現在にかけて一貫して右肩上がりの増加傾向が続いています。デジタル化の加速やDX人材の需要増を背景に、エンジニア職を中心とした求人が年々拡大しています。
特にAI・クラウド・セキュリティ領域での求人が顕著であり、2025年に入ってからも勢いは衰えていません。
- 医療・福祉業界
2024年中盤に求人数がピークを迎えたのが特徴です。これは高齢化の進行や医療機関の人手不足の影響によるもので、介護職や看護職を中心に需要が高まりました。
ただし、2025年に入ってからはやや落ち着きを見せつつあります。
- 建設業界
2023年から2025年まで通年で高水準の求人数を維持している点が注目されます。インフラ整備や都市開発プロジェクトの継続により、施工管理や設備技術者などの職種で慢性的な人手不足が続いている状況です。加えて、技能労働者の高齢化に伴う若手採用ニーズも根強く、安定した求人需要が見られます。
このように、業界ごとの求人動向を把握することで、求職者の動き方や採用の勝ち筋を読み解くヒントが得られます。特に採用競争が激しい業界では、時期とターゲットに応じた戦略的な採用活動が必要不可欠です。
業界によって求職者の動き方や求人の出方に差があります。求人数が増加しているということは、裏を返せば競争も激化しているということ。自社の求人が埋もれないよう、戦略的な求人公開時期の選定が重要です。
まとめ
中途採用市場では、求職者の行動パターンや市場の動きを読み取ることが、成功のカギを握ります。1月・2月のように活動が集中する時期に加え、ボーナス月や異動タイミングを意識した採用計画が、より戦略的な人材確保につながります。
また、通年採用の流れが進む中で、単発的な採用活動ではなく、年間を通した採用スケジュールと柔軟な採用体制の構築が企業に求められています。自社の魅力を明確に打ち出し、求職者に「選ばれる」ための情報発信やスピード感のある選考体制を整えることが重要です。
さらに、業界特性や職種別の求人数の動きにも注意を払い、適切なタイミングでの情報発信と、ターゲットに合った訴求内容の工夫を行うことで、採用の成功率を高めることが可能です。
今後も変化が予想される転職市場に対応するため、定期的な市場トレンドの確認と、採用戦略の柔軟な見直しを行っていきましょう。
出典:
https://www.r-agent.com/business/knowhow/article/18878/
https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/saiyo/00055/
https://www.neo-career.co.jp/humanresource/knowhow/a-contents-middlecareer-tyuutosaiyou-jiki-1011/