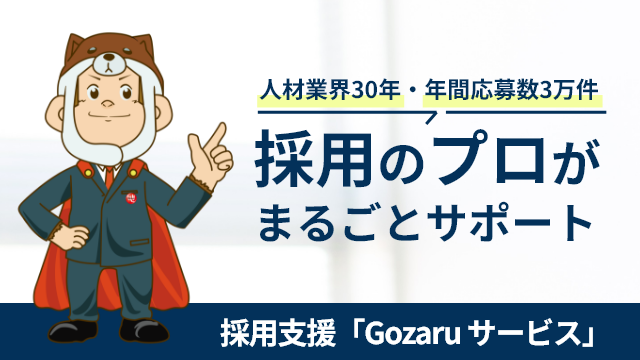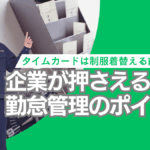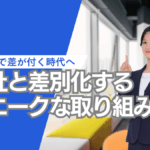企業が従業員に支払う給与制度は、採用活動や人材定着に直結する重要なテーマです。特に「月給」と「月収」という言葉は、日常的に使われているものの、多くの人が正確に区別できていません。両者を混同すると、求人広告や面接時の説明において応募者に誤解を与え、内定辞退や早期離職につながるリスクがあります。
例えば「月給30万円」という表現を見た求職者が「手取り30万円」と誤解した場合、実際に入社して手取りが25万円程度だったと知れば、不信感を抱きかねません。企業にとっては、せっかくの採用コストが無駄になる恐れもあるのです。
本記事では、月給と月収の違いを正しく理解し、人事担当者が採用活動や制度設計で活かせる具体的な方法をご紹介します。
「月給制」とは?
「月給制」とは、従業員に対してあらかじめ固定額を毎月支給する給与体系のことです。
一般的には、基本給に役職手当や住宅手当などの固定的な手当を加えた金額が「月給」として設定されます。たとえば「月給30万円」とあれば、30万円が毎月支給される仕組みです。
月給制のメリットは、企業にとっては人件費の予測がしやすく、従業員にとっては毎月の収入が安定する点です。生活費や住宅ローン、教育費などを計画的に管理できるため、安心感を持って働けるのが特徴です。
一方でデメリットも存在します。
残業代や歩合給といった変動報酬が別途発生する場合、月給だけを見ても実際の給与水準を正しく把握できません。そのため「月給=給与のすべて」と誤解されると、給与説明に齟齬が生まれることになります。
人事担当者は、この「月給制」という制度があくまで給与の一部を示すものだという点を社内外に周知する必要があるのです。
「月収」とは?
「月収」とは、従業員が1か月間に実際に受け取る給与の総額を指します。
月収は月給に加えて残業代や各種手当、交通費などを合算した金額です。企業によっては、年2回の賞与を12カ月で割って「月収例」として記載するケースもあります。
ただし「月収=手取り」ではありません。月収は税金や社会保険料が控除される前の「総支給額」です。実際に銀行口座に振り込まれるのは、そこから差し引かれた「手取り額」となります。つまり、同じ「月収30万円」であっても、扶養家族の有無や居住地による住民税の違いによって、手取り額が人によって数万円単位で異なることもあるのです。
このように、月収という言葉を使う際には「総支給額なのか、それとも手取りなのか」を明確にする必要があります。人事担当者がこの点を曖昧にしたまま求人票や説明会で言及すると、従業員との間にトラブルを引き起こす要因になりかねません。
月給と月収の違いを具体例で比較
では、具体例を交えて「月給」と「月収」を比較してみます。
たとえばある従業員の給与条件が「月給30万円」だったとしましょう。基本給と手当を含めた固定額が30万円であり、これが月給です。
しかし、その月に残業を20時間行った結果、残業代として5万円が加算され、さらに交通費1万円が支給された場合、総支給額は36万円になります。これが「月収」にあたります。
さらに社会保険料や所得税、住民税といった控除が合計で6万円差し引かれたとすると、最終的に口座に振り込まれるのは手取り30万円です。
つまり、「月給=30万円」「月収=36万円」「手取り=30万円」といった具合に、それぞれ異なる数字が並びます。
この違いを正しく説明できなければ、従業員は「求人情報に書かれていた30万円と実際の振込額が違う」と感じてしまい、不信感を募らせる原因になります。
採用活動においては「月給30万円(基本給+手当)」「想定月収36万円(残業代・交通費含む)」「手取り約30万円(社会保険料控除後)」のように段階的に明記することが重要です。こうした丁寧な表現は、候補者との認識のずれを防ぐだけでなく、企業の誠実さを示すことにもつながります。
企業が押さえておくべきポイント
多くのBtoB企業では、専門性の高い人材や営業職など、給与体系が複雑化しやすい職種を多く抱えています。そのため「月給」と「月収」の違いを正しく理解し、適切に説明できる体制が求められます。
まず大切なのは情報の透明性です。月給は固定部分であり、月収は変動を含む総支給額であることを明示しましょう。求人情報では「月給」と「月収」を混在させず、用語の使い分けを徹底することが必要です。さらに「モデルケース」を提示することで候補者の理解を助けられます。たとえば「入社1年目社員:月給25万円、残業代・交通費含む想定月収30万円、手取り24万円」といった具体的な数字を示すのです。
また、税制や社会保険制度は毎年のように改正されるため、手取り額は必ずしも一定ではありません。人事部門は最新の法改正に対応し、FAQや給与シミュレーションを更新する体制を整えておくと安心です。社員からの問い合わせに素早く回答できれば、制度に対する不安感を払拭し、社内の信頼性を高められます。
採用・人事設計における活用術
採用活動では、給与に関する情報が候補者に与える印象は非常に大きなものです。月給だけを示すよりも、月収や手取りの目安を併せて提示することで、候補者は入社後の生活をよりリアルに想像できます。これにより、条件の誤解や入社後のギャップを最小限に抑えられます。
また、内定通知やオファーレターにおいても、単に「月給30万円」と記載するのではなく、「月給30万円(基本給+固定手当)、残業代や交通費を含む想定月収36万円、控除後の手取りはおおよそ30万円」といった形で詳細を伝えることが重要です。こうすることで、候補者が安心して意思決定できる環境を整えられます。
さらに、入社時のオリエンテーションでは給与明細の読み方を説明するのも有効です。月給制と月収の違いを図や具体例で解説することで、従業員の理解度は格段に上がります。現場マネージャーも給与に関する質問を受ける立場にあるため、統一的な説明ができるよう研修を実施するとよいでしょう。給与をめぐる不信感を減らし、従業員満足度の向上につなげることができます。
まとめ
給与にまつわる誤解で特に多いのが、「月給=手取り」という思い込みです。
実際には税金や社会保険料が差し引かれるため、月給の金額がそのまま振り込まれることはありません。また、「月収は毎月一定」と考えてしまうのも誤解です。残業代や手当の有無によって月収は大きく変動するため、同じ月給でも人によって受取額は異なります。
月給はあくまで固定的に支払われる金額を示し、月収は残業代や手当を含めた総支給額、手取りはそこから控除を差し引いた最終的な受取額です。こうした違いを明確に伝えることで、採用活動や人材定着における信頼性を高められます。
さらに、社会保険料率や税制は毎年のように改正されるため、モデル月収や手取り額は一定ではありません。求人票や社内説明資料では用語を統一し、情報を定期的に見直す仕組みを整えましょう。
本記事で紹介したポイントを実務に取り入れることで、透明性のある給与制度を構築し、長期的に人材を確保するための重要な基盤となります。
出典:
https://doda.jp/guide/money/034.html
https://domani.shogakukan.co.jp/1103533