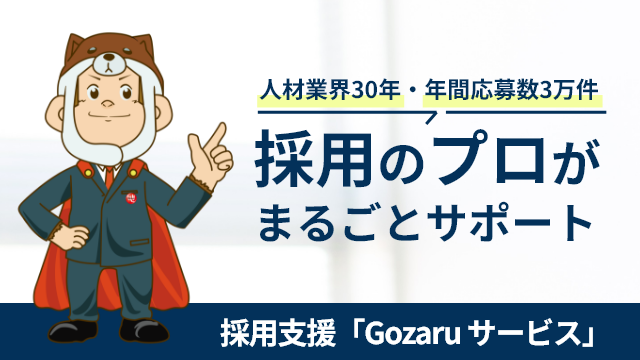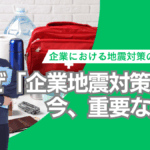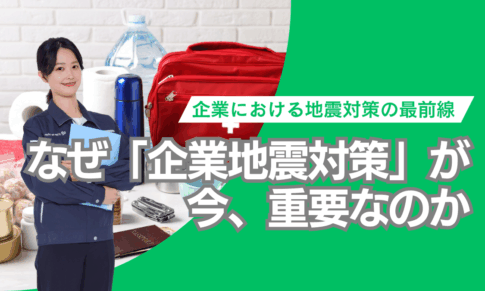「これってハラスメントになるのでは?」
職場でそう思いながら、言葉を飲み込んだ経験はありませんか。
「Job総研」が2023年3月に実施した「ハラスメントの境界線調査」では、20~50代の社会人男女354人が、職場でのハラスメントに対して敏感になっている実態が明らかになりました。
現代の職場では、パワハラ・セクハラはもちろん、モラハラ、マタハラ、テクハラ、スメハラなど、さまざまな「〇〇ハラスメント」が存在し、上司や同僚とのコミュニケーションが慎重になりすぎているケースもあります。
このような状況では、職場全体の雰囲気が萎縮し、業務効率の低下や人間関係の悪化につながるリスクも無視できません。本記事では、ハラスメントへの適切な向き合い方と、過剰反応を防ぐ「境界線」の共有方法についてご紹介します。
増え続ける「○○ハラスメント」の種類
社内で起こりうるハラスメントは、ここ数年で驚くほど多様化しています。
まず、一般的に知られている代表的なハラスメントには、以下のようなものがあります。
- パワハラ(パワーハラスメント) 上司からの威圧的な言動や不当な業務指示
- セクハラ(セクシュアルハラスメント) 性的言動による不快感
- モラハラ(モラルハラスメント) 人格否定や無視などの精神的圧力
- マタハラ(マタニティハラスメント) 妊娠・出産・育児に関する差別的対応
- ジェンハラ(ジェンダーハラスメント) 性別役割に基づく差別的言動
- リモハラ(リモートハラスメント) 在宅勤務者への監視・過干渉
- アルハラ(アルコールハラスメント) 飲酒の強要や席上での不適切な言動
- スメハラ(スメルハラスメント) 体臭・香水などに関する不快感の押しつけ
これらは、厚生労働省や各企業の就業規則にも記載される「社内で日常的に起こる可能性の高いハラスメント」です。
一方で、新しい形のハラスメントも登場しています。たとえば、
- テクハラ(テクノロジーハラスメント) IT機器の操作ミスを過度に叱責する行為
- カスハラ(カスタマーハラスメント) 顧客からの理不尽な要求や暴言への対応負担
- エイジハラ(エイジハラスメント) 年齢による偏見や排除
- ハラハラ(ハラスメントハラスメント) 必要な指導を過剰な糾弾で妨げる行為
このように、「どの言動がハラスメントに該当するのか」が個人の価値観や世代によって異なり、職場でのコミュニケーションを難しくしている要因の一つになっています。
こうした環境下では、上司が注意や助言を控えざるを得ない空気が生まれており、それが教育・育成の機会の損失にもつながっています。
「境界線がわからない」上司と「敏感すぎる」部下
「年齢や性別を気にしすぎて、何を話してよいかわからない」
「“それハラスメントですよ”という一言が怖くて話せない」
Job総研の調査では、このような声が多数見られました。さらに、「過去には笑って済んでいた話題が、今は問題視される」と感じている上司も増えているといいます。
また、労務管理研究所のレポートによれば、「叱ること=パワハラ」と捉えられるのを恐れて、管理職の約6割が“正しく指導できていない”と自覚しているという結果も出ています。
実際、ある企業では、30代のマネージャーが部下の報告に対して「それでは困る」と言っただけで、ハラスメントとみなされ人事相談に発展しました。結果的には問題なしと判断されたものの、指導する側には心理的負担が残ったそうです。
一方で、人事部門に寄せられる相談は、主観的な感情によるものも多く、どこまでが業務指導で、どこからがハラスメントなのか判断が難しいという声もあります。つまり、誰もが“被害者にも加害者にもなり得る”時代に入っているのです。
「ハラハラ(ハラスメントハラスメント)」という新たな問題
「それ、ハラスメントですよ」と強く指摘されることで、相手との関係が壊れてしまう。
そんなケースが増えている今、「ハラスメントの指摘そのものがハラスメント化する」という“ハラハラ(ハラスメントハラスメント)”という言葉が注目されています。
SNSを中心に広がったこの概念は、「行き過ぎた正義感」や「断定的な非難」が、かえって職場の信頼関係を壊してしまうことを示唆しています。指導も注意も雑談もできない──このような状況では、健全な職場とは言えません。
たとえば、「飲み会に誘っただけでアルハラと言われた」「体調を気遣ったつもりがセクハラに」といったすれ違いも少なくありません。
「伝え方」に注意することは重要ですが、「伝えない選択」をするのは本末転倒です。
境界線の認識を共有するには
このような課題を乗り越えるには、境界線を共通認識として持つことがカギです。以下の施策を継続的に行うことで、対話の質を保ちつつトラブルも防止できます。
- ガイドラインの整備と更新
企業文化に即した「してはいけないこと」「してよいこと」を文書化し、定期的に見直す体制を作ります。 - 体験型研修の導入
講義型だけでなく、ロールプレイなどを取り入れることで、「どの言動が誤解を生むのか」を体感的に学べます。 - 社内相談窓口・メンター制度の設置
匿名性を確保し、心理的安全性のある相談チャネルを複数用意することで、社員の不安を軽減します。 - 「ハラハラ」への対応ルールの明示
正当な注意・指導ができるよう、過剰な糾弾や揚げ足取りへの対応方針も明文化しましょう。
まとめ
ハラスメントを恐れるあまり、沈黙を選ぶ人が増えている今、企業が目指すべきは「何も言わない職場」ではなく、「互いに尊重しながら話せる職場」です。
指導すべきことを伝えられず、誤解を恐れて関係を深められない組織は、育成やマネジメントの機能を失ってしまいます。だからこそ、曖昧な“個人の感覚”に頼るのではなく、共通の判断軸を明確にしておくことが重要なのです。
企業の規程や対応フローは、一度作ったら終わりではありません。社員の声を吸い上げながら、常に現場のリアルに即した形でアップデートし続けましょう。
ハラスメントのない職場とは、「何も言わない職場」ではなく、「安心して話せる職場」。
その第一歩として、まずは貴社のハラスメント対応方針を再確認してみてはいかがでしょうか。
https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=2184
https://www.fnn.jp/articles/-/512914
https://ksrfp.com/labor-management/4022/