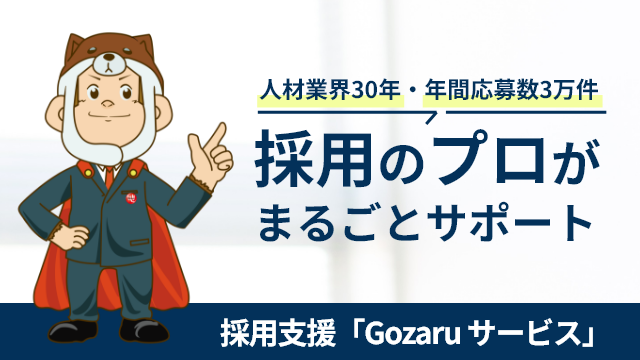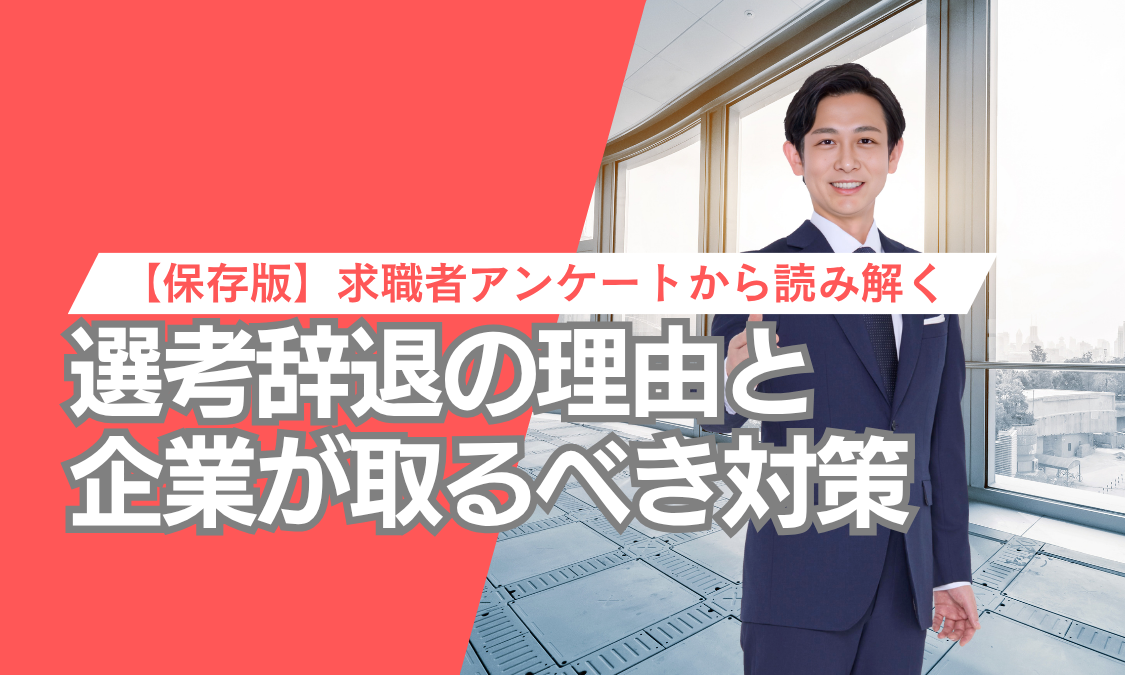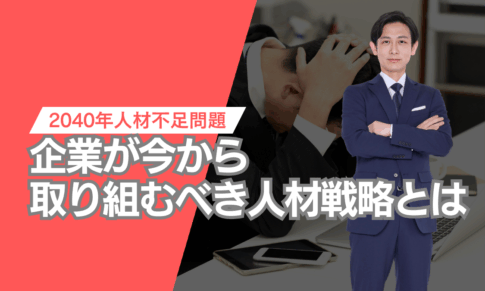採用現場で今、深刻な課題として挙がっているのが「選考辞退」です。ある調査によると、企業の85%が選考辞退を経験し、求職者の61%が何らかの理由で辞退を選んでいるというデータもあります(マイナビ転職2023年調査)。
中小企業にとって、せっかく苦労して集めた応募者が途中で離脱してしまうのは、時間的・人的コストの面でも大きな痛手です。
特に、採用業務を兼務している方にとっては「何が悪かったのかが分かりづらい」「改善策が見えづらい」と感じる場面も多いでしょう。そこで本記事では、選考辞退の理由を分類・整理し、中小企業が実行できる具体的な対策を解説していきます。
「また辞退された…」と悩まないために、応募者側のリアルな心理を押さえ、辞退されにくい採用活動のヒントを探っていきましょう。
なぜ選考辞退が増えているのか?背景を整理
まずは、辞退が起きる理由を大きく5つに分類して見てみましょう。以下は、求職者アンケートや人材会社の調査結果から見えてくる主な理由です。
- 売り手市場による「選択肢の多さ」
今は完全な「売り手市場」。
特に若手人材を巡る競争は激化しており、求職者は複数企業から内定を得て比較・選択するのが当たり前になっています。
そのため、選考のスピードが遅かったり、印象がいまひとつだった企業は、比較の中で脱落していくことになります。
よくある例:
・他社の選考スピードが早く、そちらで内定を獲得
・あくまで「本命企業の練習」で応募していた
・条件面で他社の方が良かった
- SNSや口コミサイトの影響
今や求職者の多くが、企業の評判を事前にネットで調べています。
「OpenWork」「転職会議」「X(旧Twitter)」などで検索され、悪い評判があると、それだけで不安になって選考辞退されるケースも。
ある若手求職者の声:
「面接に行く前に口コミを見たら『パワハラ体質』『残業多い』と書かれていて、怖くなって辞退しました」
- 条件・社風のミスマッチ
面接の中で、求人票と条件が違っていたり、想像と雰囲気が違うと、「ここは違うな」と思われてしまいます。
給与・勤務地・福利厚生などのハード面に加えて、「話し方」「清潔感」「社員の雰囲気」などのソフト面も重視されます。 - 応対や雰囲気の悪さ
面接官の態度がぶっきらぼうだったり、待ち時間が長すぎたり、質問内容が一方的だったりすると、応募者に不信感が募ります。
「人間関係が悪そう」「入社後も冷たくされそう」と感じさせる対応は、即辞退につながるリスクがあります。 - 家族・前職など外的要因
求職者が前職から引き留められた、家族から反対されたなど、自社には直接関係のない理由で辞退されることもあります。
こういった要因はコントロールが難しいですが、「それでも行きたい」と思わせる魅力があれば回避できる場合もあるのです。
辞退の「タイミング別」理由と傾向
選考辞退が発生するのは、大きく3つのタイミングに分かれます。タイミングごとに辞退理由の傾向を見てみましょう。
- タイミング①:面接前の辞退(エントリー直後)
主な理由
・他社の選考が先に進んだ
・口コミが悪かった
・応対が遅く不安を感じた
・忙しくなり都合がつかない
・急に不安になり自信を失った
対策のポイント
この段階での辞退を減らすには、応募受付直後のスピーディな連絡と、「選びたくなる会社」感の打ち出しがカギです。
- タイミング②:面接後の辞退
主な理由
・話してみたら印象が違った
・求人票と実態にギャップがあった
・面接官が不親切だった
・オフィスの雰囲気が暗かった
・他社の条件が良かった
対策のポイント
面接は応募者にとって最も企業の「実像」が見えるタイミング。ここでの辞退を防ぐには、丁寧な応対と本音の共有が求められます。
- タイミング③:内定後の辞退
主な理由
・他社の条件が良かった
・不安が拭えなかった
・入社後のイメージが湧かなかった
・家族に反対された
対策のポイント
内定後は「入社を後押しする最後の一手」が重要です。企業側からのフォロー連絡や、社員との座談会・カジュアル面談の提案などが効果的です。
辞退防止のための5つの実践策
ここでは、中小企業でも実践できる「選考辞退を減らすための具体策」を5つご紹介します。
- 選考プロセスの見直しと短縮化
・面接回数を1〜2回に絞る
・書類選考の基準を明確にして即対応
・オンライン面接の導入でリードタイムを短縮
特に人手が足りない企業ほど、選考の効率化が辞退防止につながることを覚えておきましょう。 - レスポンスは「即日」を目指す
応募者は複数の企業にエントリーしているため、「連絡が早い企業」に信頼感を覚えます。
書類選考の合否通知や面接日程調整は、なるべく24時間以内に対応することをおすすめします。 - オンライン選考の活用
対面面接だけでなく、ZoomやGoogle Meetなどを活用したオンライン面接も積極的に取り入れましょう。
遠方や在職中の応募者、育児・介護などで移動が難しい人にも配慮できます。 - 求人情報を「読みたくなる内容」にする
・条件面は正確に、嘘や誇張はNG
・社風、働く人、やりがいを具体的に記載
・「社員インタビュー」「1日の流れ」など、入社後のイメージを具体化
これにより、求職者が「自分が働いている姿」を想像しやすくなり、辞退リスクが下がります。 - SNS・自社サイトでの発信強化
採用情報だけでなく、働く社員の声や社内イベントの様子なども積極的に発信することで、企業の「中身」を伝えることができます。
情報が多いほど、応募者の安心感につながります。
信頼関係の構築こそが最終対策
辞退の根底にあるのは「不信感」と「不安感」です。
逆に言えば、信頼が構築されていれば、多少条件が劣っていても「この会社で働きたい」と思ってもらえる可能性が高くなります。
信頼関係を築くためには
・応募者の話に耳を傾ける
・嫌な質問でも、丁寧かつ誠実に返す
・不安を先回りして解消する情報を伝える
・選考の各段階で「気づかい」を見せる
例:「入社したら一緒に〇〇してみましょう」など、未来を想起させる声かけも効果的です。
小さな工夫が辞退率を下げる
選考辞退は、企業のイメージ・応対・スピード・誠実さ___
すべての要素が積み重なって起きる現象です。
特に中小企業は、知名度や条件で大手に勝つのは難しいからこそ、「人と人」として誠実に向き合う姿勢が最大の武器になります。
明日からでも実行できる工夫を少しずつ重ねていくことで、
「この会社、いいかも」と思ってもらえる場面が確実に増えていくはずです。
出典:https://employment.en-japan.com/enquete/report-98
https://www.works-i.com/surveys/item/240606_midcareer.pdf
https://partners.en-japan.com/special/241015/