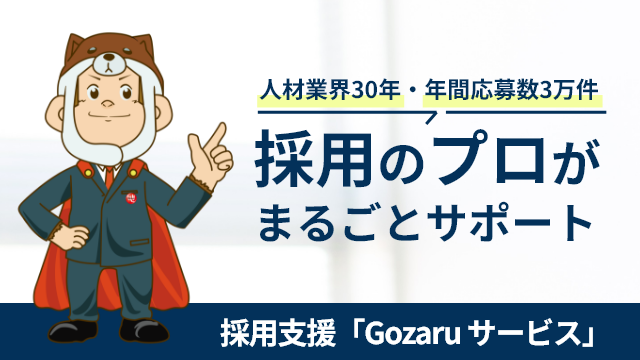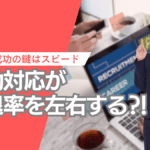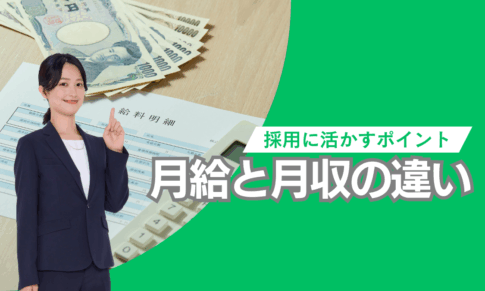近年、政府は「働き方改革」の一環として副業や兼業、いわゆるWワークを推進しています。背景には、日本全体の人手不足や終身雇用制度の揺らぎ、さらには人生100年時代を見据えたキャリアの多様化があります。副業は単なる収入補填の手段にとどまらず、個人のスキルアップや社会とのつながりを広げる働き方として注目を集めています。
従来は多くの企業が副業を禁止していましたが、厚生労働省が公表した「モデル就業規則」から副業禁止規定が削除されたことで、状況は大きく変化しました。こうした政策的な後押しもあり、企業においても「副業解禁」という言葉を見かける機会が増えています。
ただし、副業解禁は単に「従業員の働き方を柔軟にする」だけではありません。実際には、企業が担うべき労務管理やコンプライアンスの範囲が広がることを意味します。たとえば、労働時間の通算や割増賃金の算定、過重労働による健康被害の防止、さらには取引先との利益相反や情報漏洩リスクなど、多方面で注意が必要です。もし企業がこうしたリスクに無防備であれば、労務トラブルや法令違反につながり、監督官庁からの是正勧告や行政処分を受けるだけでなく、企業ブランドそのものが毀損する危険性もあります。
実際に、副業を認めた企業の中には「本業に支障が出て納期に遅延した」「副業先との間で労働時間が重なり、残業代の未払いを指摘された」といった事例も存在します。法人向け企業においては取引先との信頼関係が最も重要であり、副業やWワークに起因する問題が企業間取引に悪影響を与えれば、単なる労務リスクにとどまらず、経営そのものに影響を及ぼしかねません。
副業に関する法律的な基本知識
副業やWワークに関連する法律の中心は、労働基準法にあります。特に重要なのは、労働時間の通算に関する規定です。労働基準法第38条は、同じ労働者が複数の会社で働いている場合、その労働時間を合算して扱うことを定めています。例えば、ある従業員がA社で1日6時間働き、その後B社で4時間働いたとすれば、合計10時間労働と見なされます。法定労働時間である1日8時間を超えているため、残りの2時間分については割増賃金を支払わなければならないのです。
さらに、労働基準法第37条では割増賃金の算定方法が規定されています。時間外労働や休日労働、深夜労働に対しては、一定の割増率で賃金を計算しなければなりません。複数の雇用先で働いている場合も、原則として労働時間を通算して残業代を算出する必要があります。企業がこのルールを無視してしまうと、未払い残業代の請求や労働基準監督署の調査に発展するリスクがあります。
加えて、就業規則との関わりも無視できません。多くの法人向け企業では、副業を全面的に禁止するのではなく、事前申請制や競業避止義務の形で制限を設けています。これは過重労働や利益相反を防止するための措置ですが、禁止そのものは法律で保障された権利ではなく、合理的な理由が求められます。実際に裁判例では、副業を一方的に禁止した企業の規定が無効と判断されたケースもあり、企業は「なぜ副業を制限するのか」を説明できるようにする必要があります。
| 項目 | 内容 | 法的根拠 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|
| 労働時間の通算 | 複数の事業主で働く場合も、労働時間は合算して判断される。 | 労働基準法 第38条 | 通算で法定労働時間(8時間/日、40時間/週)を超えると割増賃金が必要。 |
| 割増賃金 | 時間外・休日・深夜勤務には割増賃金の支払い義務がある。 | 労働基準法 第37条 | 未払いは法違反。副業先での残業も通算対象になる場合がある。 |
| 就業規則の定め | 副業を全面禁止することは原則困難。合理的な理由が必要。 | 労働契約法 第3条ほか | 競業防止や業務への支障など、限定的な場合のみ制限が認められる。 |
割増賃金を巡る実務上の注意事項
副業やWワークが広がる中で、法人向け企業が特に注意すべきなのが割増賃金の扱いです。理論上は労働時間を合算して計算しなければならないのですが、実務上は従業員が副業先でどのように働いているかを正確に把握することは容易ではありません。例えば、本業の企業が従業員の副業時間を十分に認識していなければ、結果的に法定労働時間を超えていても割増賃金が支払われていない状態となり、違法性を問われることになります。
このようなリスクを回避するためには、労働契約書や労働条件通知書において、副業に関する労働時間の申告方法や報告義務を定めておくことが有効です。従業員自身が副業の勤務時間を企業に開示する仕組みを整えておけば、企業としても割増賃金の算定や労働時間管理をより正確に行うことができます。
また、副業による過重労働が従業員の健康を害した場合、企業が安全配慮義務を果たしていないと判断されるケースも考えられます。労働基準法だけでなく、労働安全衛生法との関連も無視できません。本業の労働時間が適法であっても、副業と合わせて長時間労働となれば、健康被害や労災認定の可能性も出てきます。特に近年では、過労死やメンタルヘルス不調に関する社会的関心が高まっており、企業は「副業による過重労働」にも目を配る必要があります。
さらに注意すべきは、割増賃金の責任分担の問題です。従業員が複数の会社で働いている場合、どちらの会社が残業代を支払うのかという論点が生じます。法律上は、通算して超過した労働時間を提供させた事業主が割増賃金を負担する義務を負うと解されますが、現実的には責任が曖昧になりがちです。このため、法人向け企業としては、従業員からの申告を基に適切に対応しなければなりません。
企業が導入すべき副業ルールとガイドライン
副業やWワークを認める企業が増える中で、法的トラブルや労務管理の混乱を防ぐためには、明確なルールと運用方針を整備することが欠かせません。
以下に、企業が導入すべき副業ルールとガイドラインのポイントを整理しました。
- 就業規則に副業ルールを明記する
副業を「認める」「禁止する」だけでなく、条件を明確にしましょう。
例:事前申請制、競合他社での勤務禁止、業務時間外に限定など。 - 事前申請・承認フローを整える
副業を希望する従業員は、会社に申請するよう定めましょう。
勤務内容や労働時間を把握することで、割増賃金や過重労働のリスクを防げます。 - 労働時間の通算・割増賃金管理を行う
本業と副業の労働時間は通算して判断します。
1日8時間、週40時間を超える部分には割増賃金が必要です。 - 競業避止条項を設ける
同業他社や取引先での副業は、情報漏洩や利益相反のリスクがあります。
合理的な範囲での「競業避止条項」を設けましょう。 - 健康管理と長時間労働への配慮
副業で労働時間が増えると、過労や睡眠不足のリスクが高まります。
勤務状況の確認や健康相談の機会を設けましょう。 - 情報漏洩・守秘義務の明確化
副業を行う社員には、社内情報を持ち出さないよう周知が必要です。
誓約書や研修を通じて意識を高めましょう。 - ガイドラインを従業員に周知・教育する
ルールを整えても、周知しなければ意味がありません。
社内ポータルや研修で定期的に伝え、運用を見直していきましょう。
これらのルールを整備しておくことで、企業は副業を健全に推進でき、労務トラブルや法的リスクを最小限に抑えることができます。
副業解禁の本質は「自由化」ではなく、「明確なルール化」です。企業の信頼性を高めながら、柔軟な働き方を支える仕組みづくりが求められています。
まとめ
副業やWワークは、従業員にとって収入を増やす手段であると同時に、キャリア形成やスキルアップのチャンスともなります。その一方で、法人向け企業にとっては労働時間の管理や割増賃金の計算、安全配慮義務の履行といった課題を突き付ける存在でもあります。
今後、副業は一部の人だけの特別な働き方ではなく、一般的な選択肢として広がっていくことが予想されます。したがって、法人向け企業は「副業禁止」という一方的な制限に頼るのではなく、法律を踏まえたうえで明確なルールを整備し、実務的に対応していくことが重要です。副業のメリットとリスクをバランス良く管理できる企業こそが、これからの働き方改革時代に信頼を獲得し、競争力を維持することができるでしょう。
さらに、企業が副業を前向きに取り入れる姿勢を示すことは、従業員満足度の向上だけでなく、新たな人材採用にも効果的です。副業を許容する柔軟な働き方を整えている企業は、求職者から「時代に合った働き方を尊重している会社」として高く評価される傾向があります。つまり、副業対応は法令遵守だけでなく、企業ブランド強化や競争力の源泉にもつながるのです。
出典元:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html