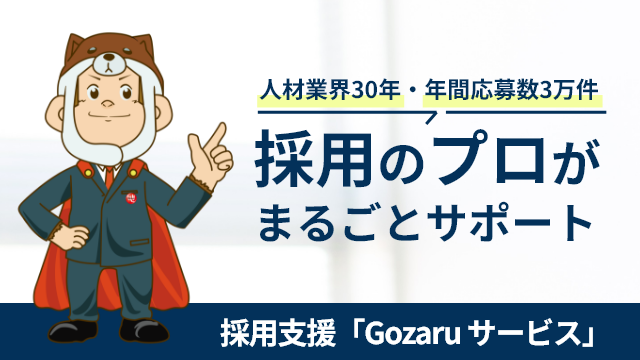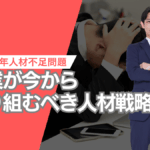近年、新卒採用市場では学生側・企業側の双方において「インターンシップ」が占める比重が高まっています。人手不足が続く中で、自社にマッチする優秀な人材を確保するため、早期からの接点づくりは不可欠です。本記事では、インターンシップの分類、学生と企業それぞれの視点、導入の狙い、そして最新の法改正の影響について解説します。
インターンシップの種類と企業が得られる効果
インターンシップは、「企業と学生が相互理解を深める機会」として、採用活動に組み込まれています。目的や期間に応じて、以下のように分類されます。
短期インターンシップ(1〜2日)
短期型は「企業を知るためのきっかけづくり」を目的としており、学生に対して会社概要や事業説明、社員との座談会などを通じて、企業文化や働き方を知ってもらいます。1dayでも「社員との関わりがあるワークショップ形式」や「模擬プロジェクト体験」など、内容を工夫することで、学生の記憶に残る印象づけが可能です。
企業側の狙いとしては、「母集団形成」の起点として、より多くの学生と早期に接点を持つことにあります。特に地方学生や学年下級生を対象に認知を広げる機会として有効です。
中期インターンシップ(数日〜1ヶ月)
中期インターンでは、実際の業務を簡易化した体験や、プロジェクトワークを通して、より深く企業の事業や働き方に触れてもらいます。学生の志望度を高め、相互理解を深めることが目的です。
この形式は、「内定後の離職リスクを軽減したい」と考える企業にとって、非常に有用です。実務体験を通じて「自社との相性」を判断してもらえるため、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。
長期インターンシップ(数ヶ月〜1年以上)
長期型インターンは、学生に業務を任せ、成果を求める実践型のプログラムです。IT・ベンチャー業界では特に一般化しており、入社前から長期的な育成が可能になるほか、OJT的にスキルを高められる点が評価されています。
企業にとっては、志望度の高い学生とじっくり関係を築きながら選考を進められるメリットがあります。加えて、若手社員や現場への刺激となり、社内の活性化にもつながるとされています。
学生の就職観とインターンシップへの期待
就職情報サイト各社の調査によると、学生のインターンシップ参加率は年々上昇傾向にあります。たとえば「6社以上に参加した」という学生が6割近くに上る調査結果もあり、就活準備として参加を重視する傾向が強まっています。
特に、下記のような傾向が見られます。
- インターン参加が「就活に対する自信」につながる
就活準備で最も力を入れた項目として「インターン参加」が1位となっており、自己理解や企業理解の一助として機能していることが分かります。
- 人気のインターン形式は「対面+短期」
オンラインよりもオフライン実施のほうが満足度が高く、理由として「社員と話せた」「職場の雰囲気を感じられた」などの声が多く聞かれます。
- 選考落ちしても再度参加したい
インターン選考に不合格でも「また受けたい」と答える学生が8割を超えており、「インターン=選考ではない」という価値観も浸透しつつあります。
また、学生がインターンを選ぶ際に重視するポイントとして、「交通費支給」「報酬の有無」「開催地域」などが挙げられます。特に、交通費支給は経済的事情から参加可否を左右する要因であり、企業側の配慮が学生の評価に直結する項目です。
企業側から見たインターンシップの戦略的価値
企業がインターンシップを導入する背景には、人材確保と育成、そして離職防止という明確な目的があります。
- 人材育成の第一歩
新卒社員を早期に戦力化するため、内定前から教育的要素を盛り込んだインターンシップを導入する企業が増えています。研修やOJT形式の業務体験を通じて、学生に「成長機会」を提供し、入社後のパフォーマンス向上につなげる考え方です。
- ミスマッチ防止による離職削減
入社後に「思っていた仕事と違う」「職場の雰囲気が合わない」と感じて離職するケースは依然として多く、企業にとって大きな損失となります。実際の現場を体験させることで、学生自身が入社後の働き方を具体的に想像でき、入社後のギャップを減らすことが可能です。
- 将来の優秀人材を早期に確保
選考だけでは測りきれない能力や人柄を、インターン期間中にじっくり観察することができます。チーム内での立ち回りや課題解決能力、主体性などを実務ベースで把握できるため、「採用の見極め」として活用される場面が増えています。
法改正とインターン活用のこれから
2022年6月、経済産業省・文部科学省・厚生労働省の三省が共同で「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を改正しました。これにより、2025年卒以降の学生から、要件を満たすインターンシップで得た情報を採用選考に活用できるようになっています。
これに該当するのは「職場での実務体験がある」「一定日数以上実施されている」などの条件を満たすプログラムで、企業側が履歴書や面接時に得られない情報を、事前に正当な方法で収集できる点が大きなポイントです。
この動きを受けて、今後は「採用直結型インターン」がより一般化すると見られており、企業も設計や運用にあたって「育成」と「選抜」を両立させる設計が求められます。
まとめ
インターンシップは、単なる就業体験ではなく、企業の採用活動における「戦略的接点」として位置づけられつつあります。採用難が続くなか、インターンシップは優秀な人材と早期に関係性を築くための貴重な機会となっており、採用後の活躍や定着にも影響を及ぼします。短期・中期・長期と多様な形式を活用することで、学生の志望度や習熟度に応じたアプローチが可能となります。
また、法改正により、一定条件を満たすインターンシップでは取得した学生情報を採用活動に活用できるようになったことから、今後は「採用直結型インターン」が主流になると見られています。学生にとっては企業理解と職業意識の醸成、企業にとっては人材育成と選抜の機会という“両利き”の制度です。
2027年卒以降の新卒採用を見据え、自社に合ったインターンシップの在り方を再設計し、より長期的・関係構築型の採用戦略を構築していくことが求められます。
「求める人材が見つからない」「採用業務に追われている」といったお悩みはありませんか?
当社では、30年以上にわたる人材派遣・紹介の実績をもとに、企業の採用ニーズに応じた最適な手法をご提案しています。
「Gozaru one」「Gozaruスカウト」「Gozaruゲート(新卒)」といったサービスを通じて、採用業務の効率化・代行をサポートしています。
どんなことでもお気軽にご相談ください。採用成功のため、全力でご支援いたします。
https://job.rikunabi.com/contents/internship/9462/
https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2337
https://www.gakuseikyosan.com/media/?p=1034